この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

体温の調節能力が問題!?
『熱中症』とは気温や湿度の非常に高い環境で体温の調節がうまくできずに起きる体の不調の総称です。多くの機関が『水分やミネラルの補給に心がけましょう!』と注意を呼び掛けていますが、実は、本当の問題は体温の調整能力にあります。水分の補給だけで予防できると思ってしまっていたら、むしろ危険です。体温調節の為の正しい知識を学び、しっかり予防しましょう!
体のたんぱく質がカギを握る
なぜ高温多湿の環境下で体温の調節がうまく出来なくなるかと言うと、体内のたんぱく質の熱変性が原因です。タンパク質=筋肉と考える人もいるかも知れませんが、体内での生理反応は伝達物質や消化酵素などたんぱく質を中心に動いています。熱中症の主な症状: 動悸、痙攣、めまい感、疲労感、虚脱感、頭痛、吐き気、などはタンパク質がうまく機能しないことにより起きます。また症状が酷くなり痙攣を起こすことありますが、これも熱により体内の酵素がうまく働かなくなり、筋内部にあるカルシウムを酵素がうまくコントロール出来なくなり起こります。
湿度・風・衣服・直射日光がカギを握る…
-
35℃の外気
-
35℃のプール
同じ温度の2つの環境を比べると、35℃のプールの中の方が過ごし安いのは確実です。プールに風が吹けば、むしろ寒さを感じるかも知れません。これは水温が体温より低い事と、皮膚に着いた水分が風によって気化熱として奪われやすくなるためおこります。体の中心部体温は約37℃なので効率よく体温を下げる事が出来れば、35℃でも快適に過ごす事は出来るのです。一方、35℃の外気の中では水中に比べ放熱効率が低下しますので、体温は上昇しやすい状態になります。ここでポイントとなるのは放熱効率です。一般的に、放熱には蒸発、対流、熱伝導や、熱放射などの物理化学的なメカニズムが関与します。高湿度、無風状態、衣服と強い直射日光などが人が放熱するメカニズムを妨げます。また、高温度のサウナの中でも熱中症を発症せずに過ごせるのは、これらのメカニズムの内一つ以上が機能しているからです。
蒸発
蒸発は汗は乾く時に気化熱として熱を奪います。しかし、発汗のみでは体温を下げるのは難しいようです。水1gが蒸発すると約0.58kcalの熱を奪います。今、70kgの人の熱容量(1℃温度を変化させるの に必要なカロリー)は70×0.83(人の比熱)=58.1kcalとなります。仮に、この人が100gの汗をかくと、0.58×100=58kcal、となり、この人の場合、100gの汗が完全に蒸発すると体温を約1℃下げる事ができます。
また不感蒸発と発汗の2つがあり、不感蒸発は体の皮膚や気道から常に水分が蒸発している状態で、1日に皮膚からは約 700ml、気道からは約300mlの蒸発があっているようです。蒸発する時に体熱が奪われて体温が下がります。外気温が29℃を超えると発汗が起こり始 めます。外気温が36℃を超えると発汗による体温低下が中心となります。湿度が高いと皮膚の汗が蒸発しにくくなり、不快に感じるのはこのためです 。
対流
熱伝導
熱伝導とは接触している物体に熱が伝わることで、プールも氷に触った時も冷たく感じ津のはこのためです。刑事ドラマなどで椅子を触り「ん?まだ温かい!敵はそう遠くまで逃げていないはずだ!」というのも熱伝導のおかげです。
熱放射
あらゆる物体はその温度に応じた振動数および強度の電磁波を放出している。これが放射です。物体の温度が高くなるにつれて、大きな振動数の電磁波ほど強く放射される傾向にあります。星などのように、高温に熱せられた物体が光を発するのはこのためです。人間の体からも接触していない物体へ熱が伝達されるますが、直射日光下では太陽のエネルギーには負けてしまいます。
発汗は個人の生活環境にもよりますが、平均的な人で1日に約600ml、夏期では約1Lになることもあるようです。スポーツなどの活動時のの発汗量を考えると、どれだけ水を飲めば良いのでしょうか?
(続く…)

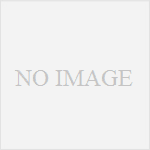
コメント